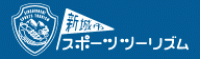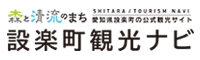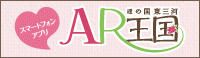動く星あれこれ
夜空を眺めていると煌めく(きらめく)星空の中を移動していく星を見ることがあります。代表的なものはパッと輝き素早く移動しながら消えていくいわゆる流れ星(流星)です。また、星空の中をゆっくりと移動していきだんだん暗くなっていくものや、だんだんと明るく輝きある程度移動したら消えてしまうものも見かけることがあります。これらは人工衛星の可能性が高いです。点滅しながら移動していくものは飛行機ですので区別することができます。今回は流星と人工衛星のそれぞれの特徴や仕組みについてお話ししたいと思います。

流星はパッと輝き一瞬にして消えてしまう華やかさと儚さ(はかなさ)があり、輝いているうちに3回願い事を唱えることができたら叶うといわれロマンチックなイメージもありますが、実際のところは、
“宇宙空間に散らばっている小さな石ころのようなものが超高速で地球に向かって飛び込んでくるときに明るく輝く現象”
と言えます。この石ころのようなものは流星物質といわれ、その大きさは直径1㎜から数㎝でその流星物質が秒速10~70㎞という超高速で地球に飛び込んでくるときに大気物質と激しく衝突して高温になり流星物質がプラズマ化して発光します。これらの現象は地上100㎞ほどの現象で夜空に輝く星々とは明らかに距離が異なります。
流星物質は宇宙空間に無数に広がっているためどの時期でも流星がみられる可能性はありますが、ペルセウス座流星群やふたご座流星群に代表される流星群の活動が活発な時期には流星物質がたくさんある場所を地球が通過しますので、普段よりも多くの流星を見ることができます。流星群については過去のコラムをご覧ください。
“宇宙空間に散らばっている小さな石ころのようなものが超高速で地球に向かって飛び込んでくるときに明るく輝く現象”
と言えます。この石ころのようなものは流星物質といわれ、その大きさは直径1㎜から数㎝でその流星物質が秒速10~70㎞という超高速で地球に飛び込んでくるときに大気物質と激しく衝突して高温になり流星物質がプラズマ化して発光します。これらの現象は地上100㎞ほどの現象で夜空に輝く星々とは明らかに距離が異なります。
流星物質は宇宙空間に無数に広がっているためどの時期でも流星がみられる可能性はありますが、ペルセウス座流星群やふたご座流星群に代表される流星群の活動が活発な時期には流星物質がたくさんある場所を地球が通過しますので、普段よりも多くの流星を見ることができます。流星群については過去のコラムをご覧ください。

人工衛星は地球観測衛星、GPS衛星、通信衛星、科学衛星など様々な目的をもっており、実際に私たちが夜空でよく見かけるものはISS(国際宇宙ステーション)やスターリンク衛星に代表される高度500㎞付近を回る低軌道衛星といわれるもので、ISSは約90分で地球を一周しています。衛星の高度が高くなるにつれてゆっくり周回するようになり地上からは、よりゆっくり動いて見えるようになります。ひまわりなど気象観測衛星は高度約3万6000㎞を周回しており地上からは同じ位置に(止まって)見えます。これらは静止軌道衛星と呼ばれており地球の自転に合わせて1日で地球1周しています。
今夜見える人工衛星の情報やISSがいつ見られるかなどの情報はインターネットの情報サイトで確認することができます。
今夜見える人工衛星の情報やISSがいつ見られるかなどの情報はインターネットの情報サイトで確認することができます。
人工衛星は現在数万個以上あるといわれておりその数は年々増加しています。夜空に輝きながら移動するその姿は美しく感じることもあります。一方で増えすぎた人工衛星が天文学の観測に支障をきたしたり、星空写真に多数の人工衛星が写りこんだりと人工衛星が宇宙の環境に様々な影響を与えています。

私たちが地球環境を守っていこうとするように、宇宙環境についても同じように守っていく意識が求められています。私たちの豊かな生活には欠かせない人工衛星ですが、このコラムが美しい星空を後世に残せるよう考えていくきっかけになればと願っています。
コラム by 奥三河星空案内人・星のソムリエ® 後藤修一
コラム by 奥三河星空案内人・星のソムリエ® 後藤修一